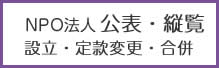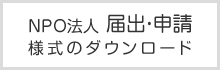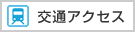埼玉県日本中国友好協会
 |
|
日中の国交が正常化されていない1950年に発足 日本と中国との国交が正常化されていない1950年10月1日、政治・経済・文化・学術など各界の有識者が発起人となり、全国組織「日本中国友好協会」が創立された。 日中両国民に悲惨な結果をもたらした戦争を再び繰り返さないため、思想・信条・政党政派の違いを越えともに友好関係を築きあげる目的であった。以来、文化・人事の交流、経済貿易の促進等、アジアと世界平和の安定に努力してきた。 埼玉県日本中国友好協会は、全国本部設立と同時に発足し、一日も早く中国と国交関係を結ぶよう運動を展開した。友好を発展させ、中国を知らせる活動として講演会や研修会、民間貿易、中国物産展などを行った。 1972年共同声明発表後、日中友好の活動は活発になり、1979年、廖承志中日友好協会を団長とする「中日友好の船 訪日団」600名が日中友好協会の招きで来日し、都道府県庁を訪問した。山西省代表団は、埼玉県への訪問を希望し、埼玉県日中友好協会の協力で実現した。 1982年10月埼玉県は「日中友好埼玉県青年の翼」を山西省に派遣し、埼玉県と山西省の友好県省協定が締結された。以後数次にわたる友好訪問を重ねて人事交流が深まっている。
60年に及ぶ埼玉県日本中国友好協会の活動事業 県協会は、各市長、議員、県内経済関係者を含む訪問団のコーディネートなどを行なってきた。また各県内友好都市と協力してその地域の特徴を生かした文化、人事、経済、学術、スポーツ等の相互交流を続けている。 「日本中国友好協会全国本部」が社団法人化したことを受けて法人化を検討し、2004年に法人の認証を受けた。 具体的な活動は、中国物産展(1971年~、さいたま市玉蔵院境内にて25回)、日中友好書道家交流展(埼玉県、中国山西省・河南省)、中国水墨花鳥展(戸田市)、在日中国歌舞団公演(県内10ヵ所)、中国河南省雑技団公演(県内7ヵ所)、黒龍江省方正地区日本人公墓修復募金、阪神大地震チャリティー音楽会、南京城壁修復募金等である。留学生の派遣は、1984年に山西大学に派遣して以来、河南・鄭州・大連外国語学院・遼寧師範北京外国語の各大学に派遣し、2009年には延べ1200名になった。また、1990年から1996年までに、県内学校法人等の協力を得て延べ230名の留学生を受け入れた。 特筆すべきは、「中国希望工程」(貧困層の児童育成援助のための基金)だ。所得の少ない地域に小学校を建立する活動で、山西省を中心に、10校を建設した。他にも、この会の呼びかけで、県内の友好団体、個人が建立した小学校は20校に及ぶ。国立中国雑技団公演(埼玉会館で2回)、中国映画上映会(県内で数回)。 現在も引き続き、留学生の派遣、中国語教室、「中国語発表のつどい」、「中国を知る」市民連続講座、「日本と中国」全国紙の普及、「日本と中国」埼玉版の発行、新年会(県内の友好を願う人士と会員が集う会)を開催し日本と中国の友好促進を進めている。 また、この会は16の地区協会の連帯組織であり、地区協会もこの会に協力し、地域に見合った独自の活動をすすめている。 |
 太原市で開催された児童絵画展 太原市で開催された児童絵画展 |

浦和で行われた日中児童絵画展 日本の子どものたちの作品 |
中国山西省の子どもたちの作品 |
|
この会が大きな事業として取り組んでいるのが、「日中緑化交流基金」を活用して行っている中国への「緑化協力事業」である。第一次事業は2004年から2008年太原市尖草坪において実施した。引き続き2009年から2011年には第二次事業を実施することとなり、太原市の西、呂梁山脈を越えた呂梁市の山中で「植生復旧模範林造成事業」を行うことになった。山西林業庁、地元関係者も協力し、2009年4月には植樹祭訪中団が現地を訪問し植樹した。 2008年上田知事は、訪中団を率い植樹祭に参加し、現地政府関係者に加えて、農業に従事する民間人、小・中学生たちと友好を誓いあった。
|
2005年太原市尖草坪で実施された「汾河生態造林緑化事業」
|
|
☆協働相手からの応援コメント☆ |
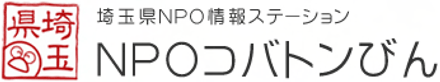
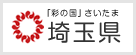
 日中児童絵画展
日中児童絵画展