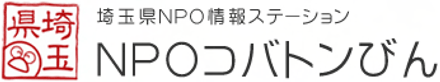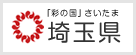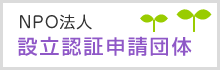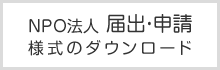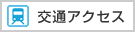セミナー「新しい企業価値の創出―経営強化につながる社会貢献とは―」を開催しました。
企業の社会貢献について、経営者は、経営戦略上、どう捉えて行けばいいのか...
単に社会的責任を果たすということだけではなく、本業の発展に結びつくような、企業価値を高める社会貢献について、会場の皆さんとともに考えるセミナーを開催しました。
日時:平成24 年2 月23 日(木)18:30~20:30
会場:大宮ソニックシティ906 会議室
講師:
渋澤 健 氏 (シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役CEO)
鵜尾 雅隆 氏 (日本ファンドレイジング協会常務理事)
【内容】
■18:35 渋澤健 講演開始(55 分)
まずは、渋澤氏より、次のような導入の話がされた。
「今日は、みなさんと、過去から学び、未来のことを考えてみたいと思う。まずは、近代日本の成立過程を振り返りながら、我々の将来のことについて考えていきたい。」
その後、渋沢栄一から現代の経営者までの社会貢献の流れの中で、日本社会の時代認識と、30 年先の未来を考える発想について講演が行われた。渋沢栄一の道徳経済合一説や著書『青淵百話』の「元気振興の急務」なども解説した。
さらに、30 年周期で時代を読み解くという視点から、近代化以降の日本社会が繁栄と破壊をそれぞれ30 年ごと繰り返してきた変化を説明。その上で、これからの企業経営のキーワードとして「枠を越える」と「共感」をあげ、今日より明日を良くしたいという共感資本により、時代の枠を超えた持続性価値を見出すことが重要なポイントになってくることを述べる。
また、「智・情・意」の三者がバランスよく発達したものが企業経営の完全な常識になることを、事例や渋沢栄一の道徳経済合一説や『青淵百話』の「元気振興の急務」などを引用しながら説明した。
1930 年から2055 年(予想)までの人口動態変化をグラフを用いて解説し、将来世代に<つけ>ではなく<希望>を残せるように、共感資本や長期投資による企業の社会貢献活動によって持続的価値の提供を行っていく必要を説く。
最後に、そのような企業行動(新しい企業価値の創造)を取るために、必要なポイントを『論語』を引用して解説した。ポイントは次の3 つ、①物事を知ることは大事、②知ることより好きであることが
大事、③好きであることより楽しむことが大事、である。
 |
■19:30 鵜尾雅隆 講演開始(30 分)
まず、企業の社会貢献がCSR の4 つのレベル、「法的責任」「倫理的責任」「経済的責任」「社会貢献活
動」のうちの一部であることを解説した。
現代の企業の社会貢献5 類型(1.社会課題のPR 活動の実施・2.寄付つき商品の販売・3.寄付や協賛・4.社員のボランティアや寄付の支援・5.社会的責任に基づく事業の実施)を総覧し、コーズマーケティング・NPO との協働が企業の本業にプラスになっているモデル、人材育成に社会貢献を組み合わせているモデルなどが、どういった発想で生まれ、新しい企業価値につながっていくか事例を交えて講演。あわせて2011 年度に大きく改善された認定NPO 法人制度についても解説。渋澤氏と同じくこれからの企業経営のキーワードとして「枠をこえる」と「共感」をあげ、この点に大きな力を秘めているNPO と、企業が協働することによってあらゆるステークホルダーに>win-win な関係を構築できることを、具体例を挙げて紹介した。
また、2011 年に大きく変わった寄付税制について、寄付の税控除が最大50%(ただし2,000 円は差し引く)ことなどを解説する。

■20:00 参加者同士で自己紹介と各講演のフィードバック(10 分)
■20:10 渋澤・鵜尾トークセッション開始
打ち合わせをしていないのにも関わらず、「枠を越える」と「共感」というキーワードが一致したことをあげ、時代がシンクロニシティになっていることを挙げる。
「時代の歯車がかみ合い始めているときに
は、別の立場の人たちが、水面下で同じ歯車をかみ合わせて回し始める。これから本格的に社会が動き始める」(渋澤)と述べる。
■20:20 質問時間
Q1.
高齢者が多くのお金を持っているが、一方で若い世代が一生懸命頑張ってもお金を貯めることができない世の中になっている。高齢者から若い世代へお金をまわす手段として何か具体的な方法はあるのか?
A1.(鵜尾)
生前贈与、高齢者の消費増大、高齢者の寄付も考えられるが、アメリカで寄付をする理由として、特にアジア系は次世代の継承のためを挙げる場合が多い。日本もアジアの国として一つの方法として、遺言で寄付をするというものがある。遺言がドラマにもなり、現在10%の遺言率も確実に増加している。また、企業でも寄付信託のような商品も生まれている。
Q2.
大きな企業やリソースがない地域(埼玉県東部)の名もない小さなNPO が、協働するために、地域でどのような働きかけをしていけばよいのか?
A2.(鵜尾)
CSR 等に積極的な比較的大きな企業を見ても、どう考えても接点のない小さなNPO とつながりを持っていることが多い。それは何かしらからの接点とご縁からつながりを持ったものがほとんど。地域活動であるならば、理事に地元の有力者や名士と言われるような人に入ってもらう。それだけでも世界が広がる。

※本セミナーは、新しい公共支援事業の一環として、事業をNPO法人日本ファンドレイジング協会に委託して実施するものです。
委託団体の情報はこちら(PDF)。